第23回眼科臨床機器研究会
日時:2024年10月26日(土) 15:30~18:30
会場:横浜シンポジア
ジョイント開催:The 27th IRSJ(2024)
日眼専門医事業認定番号:12745
主催 眼科臨床機器研究会
会長 庄司 信行(北里大)
事務局長 飯田 嘉彦(北里大)

第23回眼科臨床機器研究会
日時:2024年10月26日(土) 15:30~18:30
会場:横浜シンポジア
ジョイント開催:The 27th IRSJ(2024)
日眼専門医事業認定番号:12745
主催 眼科臨床機器研究会
会長 庄司 信行(北里大)
事務局長 飯田 嘉彦(北里大)
プログラム
1)広角OCT
DRI OCTTriton Pro モデレーター/柳田 智彦(北里大)
・Triton発売からの進化 山田勝啓(㈱トプコンメディカルジャパン)
・Triton Proの使用経験 河野雄亮(北里大)
2)OCTと最新の視野計による緑内障管理 モデレーター/笠原 正行(北里大)
・C I R RUS-5000OCTによる緑内障進行速度 小川俊平(東京慈恵医大)
・コーワAP7700の有用性 朝岡 亮(聖隷浜松病院眼科)
・Imovifa 野本裕貴(近畿大)
3)デジタルディバイスで患者を救う モデレーター/平澤 一法(北里大)
・Smart Eye Cameraで患者を救う 清水映輔(株式会社OUI/慶應大)
・診断 ・ 治療用アプリの眼科臨床応用に向けた研究開発
猪俣 武範 (順天大/順天大大学院医学研究科AIインキュベーションファーム)
・視覚障害者のICT活用とビジョンケア
三宅 琢(公益社団法人NEXT VISION/Studio Gift Hands)

1)広角OCT DRI OCTTriton Pro
モデレーター/柳田 智彦(北里大)
トプコン社のDR I OCT Triton Proは、 最近普及し始めているスウェプトソース方式のOCTで、従来のスペクトラルドメイン方式と比べ、スキャン速度が速く、高い組織侵達性と深さ方向の信号低下が少ないことで、 硝子体から脈絡膜、
強膜までをより詳細に描出できるようになっています。同社のDRI OCT Tritonは2015年に発売されていますが、Triton Proには広角OCT撮影用アタッチメントレンズと、 IMAGEnet6にSmart Denoiseというアプリケーションが追加されています。 アタッチメントレンズを付けることでより広範囲に撮影できるようになり、 Smart Denoiseでノイズの少ない画像が得られるようになりました。
講演Ⅰでは、 まずトプコンメディカルジャパンの山田勝啓氏に機器の概要についてお話していただき、 次に北里大学の河野雄亮先生に使用経験を講演してもらうことになっています。
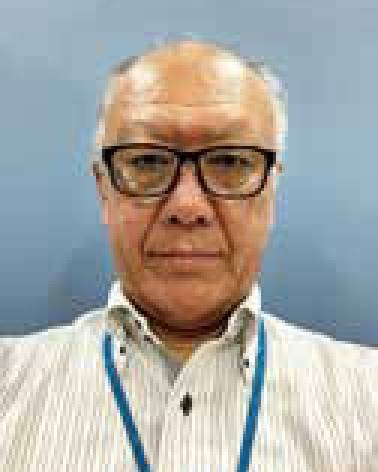
◆ Triton発売からの進化
講演者:山田勝啓(㈱トプコンメディカルジャパン企画部プロェッショナル)
1990年 株式会社トプコンメディカルジャパン入社
1995年 名古屋営業所所長
2009年 本社技術企画部部長
2011年 本社営業本部部長
2012年 本社販売推進部専任部長
2018年 本社販売推進部上席専任部長
2020年 本社営業技術統括部統括部長
2024年 本社営業企画部プロフェッショナル
Tritonは、
2014年10月に世界初SS-OCT(Swept-source optical coherence tomography)の「普及機」として発売されました。
今回は、Tritonの基本性能、特化した性能、追加された機能、オプション機能(有償)、OCT Angiographyに追加された機能、NEWモデル「TritonPro」に追加された機能をご紹介させて頂きます。
1.SS-OCTはSD-OCT(Spectral-domain)と比較して、 大きく2つの効果が有ります。
①SS-OCT効果:深さ方向の信号減衰が少なく、 硝子体から脈絡膜強膜撮影が可能
②長波長効果:高侵達=中間透光体混濁撮影に有利、 被検者より不可視、固視の安定
2.無散瞳眼底カメラ(カラー眼底)との複合機、 幅広いNormativeData(12×9㎜)搭載
3.Triton plusモデルは、 FA(蛍光眼底撮影)FAF(自発蛍光眼底撮影)
4.NEWモデルTriton
Proでは、Smart Denoise(AI Denoise機能)、前眼部解析(隅角計測・角膜厚計測)まで可能と成り、全ての機種で使用できるWA-1(広角撮影アタッチメント)も追加発売されました。Tritonシリーズは、OCT検査の多様化に伴い、検査の効率化を目指して、進化を続けて行きます。
【利益相反公表基準】 [E] 株式会社トプコンメディカルジャパン [E]

◆ Triton Proの使用経験
講演者:河野 雄亮(北里大)
2012年 聖マリアンナ医科大学 医学部 卒業
2014年 北里大学病院眼科学教室入局
2018年 北里大学医学部助教
2023年 北里大学医学部診療講師
OCTは黄斑部疾患や網脈絡膜疾患を含む様々な網膜疾患や、緑内障の早期発見、
経過観察、 定量的評価を行う為に必須の検査機器である。
近年Swept Source方式を採用したOCTが普及しており、 その代表がTOPCON社のTriton Proである。 以前の機種と比べ高速撮影が可能となり、 AIによるノイズ除去処理(デノイズ)機能によりノイズの少ない鮮明な画像の描出が可能となった。また、広角OCT撮影用アタッチメントを使用することで21㎜のスキャン幅を持つ、 OCTおよびOCT-Aの画像が取得可能である。 今回はその使用経験について述べる。
【利益相反公表基準】 該当なし

2)OCTと最新の視野計による緑内障管理
モデレーター/笠原
正行(北里大)
緑内障診療において、視野検査は進行速度を評価する上で最も重要な検査といえます。しかし、 構造的変化がメインの極早期緑内障においては、
視野検査で機能的な変化を評価することが難しい場合も少なくありません。 また、 視野検査がうまくできない症例においても他覚的検査が重要となり、 光干渉断層計(OCT)の進歩に期待が寄せられます。 また、視野検査の精度を向上させようとすると、 検査時間が長くなり、 患者、 医療者側ともに負担が生じておりました。本セッションでは、
前半に、 構造的な緑内障管理として、CI RRUS-5000 OCTを用いた緑内障進行速度評価について御講演頂きます。
後半では、機能的な緑内障管理として、 精度を落とさずに、 より短時間での検査を目指した新しいアルゴリズムが搭載されているコーワAP7700の有用性について、 最後に、 コンパク トかつ明所で行うことができ、独自の測定プログラムも搭載されたimo vifaについて、3名の演者に御講演頂きます。 本講演が明日からのより良い緑内障診療につながることを期待しております。

◆
CIRRUS-5000OCTによる緑内障進行速度
講演者/小川 俊平(東京慈恵医大)
略歴
2003年 東京慈恵会医科大学
2008年 東京警察病院眼科
2010年 東京慈恵会医科大学眼科
2012年 スタンフォード大学心理学部留学
2015年 厚木市立病院眼科診療医員
厚木市立病院眼科上席医長
2017年 東京慈恵会医科大学 眼科 講師
緑内障の診断は“ 機能的・構造的異常”の整合性を総合的に判断することで行われる。
構造異常の評価法である光干渉断層計(OCT)の目覚ましい進歩により、機能評価の静的自動視野検査(SAP)との間に異常検出時期に差が生じ、 前視野緑内障が定義された。 自覚検査であるSAPには、検査精度、検査時間、患者疲労など、多くの問題が残されている。また、極初期や後期ではSAPでの進行評価自体が出来ないことも少なくない。このため、他覚検査で、かつ測定誤差の少ないOCT に診断や進行評価のブレークスルーが期待されている。 本講演では、 当院でのC I
RRUS-5000を用いた緑内障診断後の進行判定についてお話ししたいと考えている。
【利益相反公表基準】 該当なし

◆ コーワAP7700の有用性
講演者/朝岡 亮(聖隷浜松病院眼科)
1996年 東京医科大学医学部医学科卒業
1996年 東京医科大学眼科
2002年 浜松医科大学眼科
2006年 日本学術振興会特定国派遣研究員
(Moorfields Eye Hospital(英国))
2008年 Moorfields Eye Hospital及びCity University London(英国)
2012年 東京大学眼科
2020年 聖隷浜松病院眼科主任医長
聖隷クリストファー大学臨床准教授
2021年 国立大学法人静岡大学電子工学研究所
ナノビジョン研究部門特任准教授
光産業創成大学院大学
光産業創成研究科客員准教授
2022年 聖隷浜松病院眼科緑内障眼科部長
2023年 聖隷浜松病院眼科アイセンター眼科部長
聖隷クリストファー大学臨床教授
2023年 国立大学法人静岡大学イノベーション社会連携推進機構客員教授
緑内障診断において視野診断が重要なことは言うまでもありません。視野検査にも様々なものがあり、 その各々に一長一短がありますが、
特に近年ではハンフリー視野計に標準搭載されているSITA法が1990年代に開発され全点閾値法から世代交代したことは非常に革新的な出来事でした。
しかしその後視野測定アルゴリズムにはそれ以上の大きな進歩は見られていませんでした。最近我々は「変分近似ベイズ推定法」という緑内障視野感度をAIを用いて推定する方法を開発しました(Beeline社HFA filesⓇにGlaPreⓇとして搭載)。 コーワAP7700にはこの方法による視野予測を用いることで、 測定精度を落とすことなく、SITAよりも高速に視野測定を行うアルゴリズム「SmartⓇ」が搭載されています。 本講演では、 この変分近似ベイズ推定法による視野予測やSm a rt Ⓡ についてご紹介させていただきたいと思います。
【利益相反公表基準】[F]Reicherttechnologies、Oculus、興和、Nidek[P]
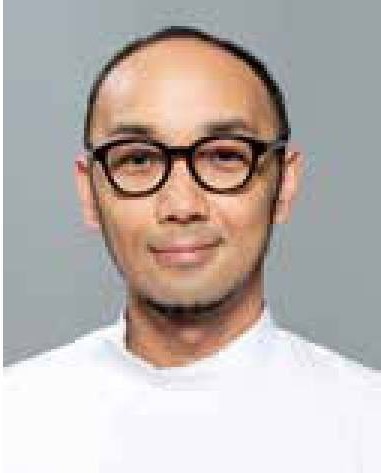
◆ imo vifa
講演者/野本 裕貴(近畿大)
2003年 近畿大学医学部卒業
近畿大学医学部眼科学教室研修医
2008年 大阪府済生会富田林病院眼科副医長
2010年 近畿大学医学部眼科学教室助教
2012年 Moorfields Eye
hospital,Honorary
research fellow
2020年 近畿大学医学部眼科学教室講師
2024年 近畿大学医学部眼科学教室准教授
眼科臨床において、視野検査は視機能評価に重要な役割を果たしていることは周知の通りです。 現在、 視野検査の際に最も頻用されているの
が自動静的視野計(SAP)であり、
1970年代の登場以降、 機器およびソフ トウエアの改良を経て現在に至っております。 imo vifaは従来のSAPと同じように自動静的視野検査を行う機器ですが、 暗所が不要、両眼開放下での同時検査、 アイトラッキング機能搭載等の他には無い機能が搭載されています。また、臨床でのニーズを意識した独自の測定プログラム、測定点配置が使用されています。加えて、imo vifaは視野検査だけでなく、 コントラスト感度測定も可能で視機能検査機としての位置付けを目指した機器となっています。本講演ではimo vifaの特徴と今後の発展性について紹介したいと思います。
【利益相反公表基準】 該当なし

3)デジタルディバイスで患者を救う
モデレーター/平澤 一法(北里大)
デジタルデバイスの発展により、眼科で使用される検査機器は著しく進歩しました。以前の検査機器は大きくて重く、 持ち運びができないため、
患者が病院に来るのが当たり前でした。デジタルデバイスの発展の代表的なものとしては、スマートフォンやタブレット端末が挙げられます。 現在のスマートフォンやタブレッ
ト端末は高解像度で軽量であるため、 かつては考えられなかった遠隔診療が可能になりました。 また、 これらのデバイスは多くの人が日常的に使用していることから、 ロービジョン患者への補助具としても活躍しています。さらに、スマートフォンは国民のほぼすべてに普及しているため、ビッグデータを収集することも可能であり、
これらのデータを解析することで患者にフィードバックすることも可能になりました。 今回、 デジタルデバイスを臨床応用している日本を代表する先生方にご講演を賜る機会を得ることができ、
大変光栄に存じます。

◆ Smart Eye
Cameraで患者を救う
講演者:清水 映輔(株式会社OU I/慶應大)
2013年 慶應義塾大学医学部卒業
2013年 独立行政法人国立病院機構東京医療センター
初期研修医
2015年 慶應義塾大学医学部眼科学教室助教
2016年 東京歯科大学市川総合病院眼科助教(出向)
2016年 株式会社OUI(OUI Inc.)起業
2019年 医療法人慶眼会理事長
2020年 慶應義塾大学医学部眼科学教室特任講師
Smart Eye Cameraは、 スマートフォンを用い、 いつでもどこでも誰でも眼科診療ができる医療機器である。 国内では、 遠隔地の診療所で
も眼科診療が可能となり、 早期発見・治療に貢献している。 海外では、
医療リソースの乏しい地域でスクリーニングツールとして活用され、 失明予防に大きな役割を果たしている。
ハードウェアの性能向上に加え、AIによる画像解析技術の進歩により、眼科疾患の早期発見早期治療に寄与、さらに、クラウドベースの画像ファイリングシステムにより、
経時的な病態変化の把握や多施設での情報共有が容易になった。
今後は、AIの精度向上と遠隔医療システムとの連携強化により、世界中のどこでも高品質な眼科診療を受けられる環境の実現を目指す。Smart Eye Cameraは、眼科医療のグローバルな均てん化に向けた重要なツールとなるだろう。
【利益相反公表基準】[F]AMED[P]

◆診断・治療用アプリの眼科臨床応用に向けた研究開発
講演者:猪俣 武範(順天大/順天大大学院医学研究科AIインキュベーションファーム)
2006年 順天堂大学医学部医学科卒業(MD)
2008年 東京大学医学部附属東大病院初期臨床研修医修了
2012年 順天堂大学大学院医学研究科医学博士課程眼科学卒業(PhD)
2012年 順天堂大学医学部眼科学講座助教
2012∼2015年
ハーバード大学眼科
スケペンス眼研究所博士研究員
2015年 ボストン大学経営学部Questrom School of Business卒業(MBA)
2019年 順天堂大学医学部眼科学講座准教授
眼科診療におけるデジタルヘルスは、眼疾患の早期発見と治療の効率化を目的とした新しいアプローチである。 デジタルヘルスには、 遠隔診療、モバイルヘルス、人工知能による解析等が含まれ、医療の質と効率を向上させる。デジタルヘルスの中でもエビデンスに基づき診断・治療・予防等への使用を目的とした製品はSaMD(Software as Medical Device)と呼ばれる。 SaM Dの中でも医学的なエビデンスに基づき診断や治療介入を提供するものがデジタルセラピューティックス(DTx)と定義される。DTxの導入により、 患者ごとに最適化された切れ目のない治療介入による診療の質の向上や、
患者や医療従事者の負担軽減が期待される。
これまで演者はスマホアプリ型 ドライアイ診断補助用プログラムや、バーチャルリアリティを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器の研究開発に取り組んできた。
そこで本講演では、 デジタルヘルスとプログラム医療機器の現状と将来展望について概観し、 眼科診療の革新における重要性を論じる。
【利益相反公表基準】
[F] ジョンソンエンドジョンソン株式会社、 小林製薬株式会社、株式会社フコク、株式会社関電工
[E]InnoJin株式会社、一般社団法人IoMT学会
[C][P]
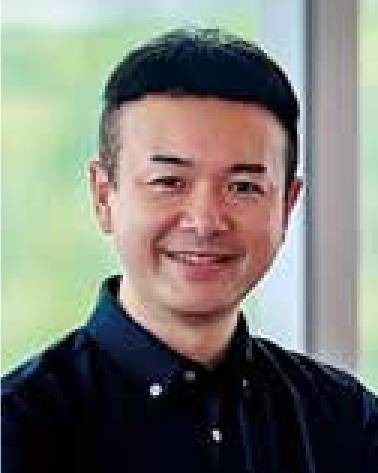
◆ 視覚障害者の
ICT活用とビジョンケア
講演者:三宅 琢(公益社団法人NEXT VISION/Studio Gift Hands)
2012年 東京医科大学大学院 修了
東京医科大学 眼科学教室 兼任助教
2013年 東京大学先端科学技術研究センター人間支援工学分野 特任研究員
2014年 神戸理化学研究所 網膜再生医療研究開発プロジェクト 客員研究員
2018年 東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員
公益社団法人NEXT VISION 理事
2019年 東京大学未来ビジョン研究センター客員研究員
2023年 公益社団法人NEXT VISION副理事長
視覚障害者はかつてより移動障害を伴う情報障害者と表現されてきた。私は眼科医、 産業医という立場で視覚障害や発達障害のある人々が情報障害に陥ることを予防し適切な合理的配慮を受けられるように、 ICT機器を用いた情報支援を行ってきた。
分野横断的な活動を通して困難さを抱える人々が医療的、社会的、心理的な回復を得られる包括的な社会の実現には、 適切な情報提供による情報障害の軽減に加えて人々の出会いと社会へ接続する機会の提供が必要であると実感している。
ウェルビーイングな未来の実現には多様な人々が自分らしく生きていける、 誰も取り残さない社会システムの構築が必要だと言われている。 本講演ではICT機器活用が有効であった事例と、 人生100年時代における治療を目指す医療と自律を目指すケアが両立する新しい医療のあり方や多様な人々が共存する社会における医療機関の期待役割などを含め簡単に解説したい。
【利益相反公表基準】 該当なし
展示機器のご紹介

● 株式会社トプコンメディカルジャパン
3 次元眼底像撮影装置DRI
OCT Triton Plus Pro

視機能評価機imo vifa

●株式会社ニデック
RS-1 Glauvas

● 興和株式会社
コーワ AP-7700

●カールツァイスメディテック株式会社
シラスHD-OCT premium(モデル6000)

● 株式会社ファインデックス
視線分析型視野計
ゲイズ アナライジング
ペリメーターGAP